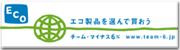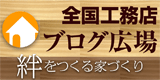風量測定。
 竣工間近です。
竣工間近です。
風量調整の為、日本住環境株式会社さんより、
気密測定士でもある、菅原さんに来ていただきました。
ありがとうございました。
この物件では3種換気、集中型換気システムを採用しています。新鮮な空気は機械を使わず自然給気で行ない、排気は一端、玄関や天井裏、パイプスペースなどに設置された、チャンバーBOXに集積し、外部へ放出する方式です。
床下も含む建物全体の必要換気量は、内部空間の容積から算出されます。
ですが各部屋からチャンバーBOXまでの配管距離、経路などの違いにより、
同じように吸引しても“吸い具合”に差が出ます。
また間取りによっては、トイレ、洗面などは他の居室よりも、
強めに吸わせたい、換気させたい、出来れば床下も。
それらの理由により、建物全体の換気量はそのまま、
部屋ごとに換気量を調節します。
まず計算式により、システム全体の換気量を設定。
その後、各部屋の天井や壁面にそれぞれ設置した換気ガラリに、
風量測定器のノズルを挿し込み、その時点での換気量(吸引力)を計ります。


ガラリ部材は2枚合わせになっており、
外側は可動式で、孔位置をずらすことで開口面積が変化します。
この部材の場合、目盛1にすると閉じ、5で全開放となります。
単純には、開口を大きくするほど、その部屋の換気量は大きくなり、
その分だけ他の部屋の換気量を奪う(減少する)ことになります。
すべての部屋、床下のデータが揃うと、それらを比較検討、
全体のバランスを見ながら、各ガラリの孔開口を微調整し、
また測定という作業を、それぞれに適切な換気量となるまで繰り返し行ないます。


現場に到着した時には、既に作業開始時間のはずが、
現場監督・軒がいません、けれどどこからか声がします。
いちぃーっ・・・・ってんごぉー・・・床下で計測中でした、軒でした。
当然、床下ももぐって出ての繰り返し。
記録確認にコーチに走り寄る陸上選手のようにも見えました。
現場写真を見ていても、こういう写真なんか多いので、
リフォームなどの現況調査でもぐる時には、
あたまいたなる(※ここ早口です。)、などと言ってはいますが、
自分たちで建てたお宅の床下の居心地はどこか違うのかもしれません。
すべての部屋の設定完了、後片付けの段、測定器のノズルが・・・・・
ト音記号でした、と書ける書こう、と思うもこう見るとそうでもないです。
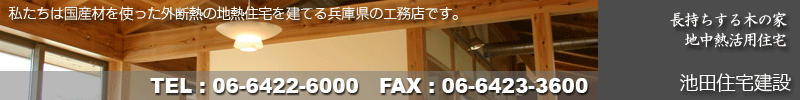
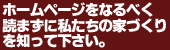
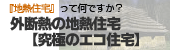
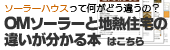
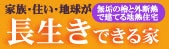
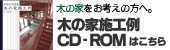
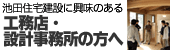
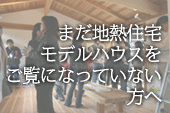
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)
![土地探しから始める家づくり。[土地情報サービス]登録はこちらから。地熱](../images/estate-a.gif)
![兵庫県西宮市・宝塚市・伊丹市で土地探しから始める家づくり。[土地情報サービス]会員ページはこちらから。地熱](../images/estatemembers-a.gif)