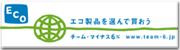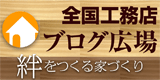国産の杉を使った無垢の家「野間の家」プロジェクト
『国産材って?』

さて、このプロジェクトを考えるにあたり、私たちも国産材について色々調べてみました。
日本では、戦後の高度成長期までは木材は国産材でまかなっていたのですが、膨大な需要に国産材の供給が間に合わなくなって、安い『外国材』が大量に輸入されるようになりました。現在では、国内の木材需要の80%をそういった輸入材が占めており、国産材需要はわずか20%。さらに現在、日本の森林の約半分が、戦後に植林された杉や桧の『人工林』なんだそうです。
この『人工林』は自然のまま放っておいてよい『天然林』とは違って、枝を落としてやったりする『手入れ』をしてやらないと、育ち放題の商品価値のない木材になってしまうんです。
ところが、安い外国産材に押され、国産材は売れない・・・ということで、林業に携わる人々は減少してしまいました。 せっかく育っても、手入れをする人がいないので森は荒れ放題・・・という状態なのです。 ちなみに平成7年1年間の森林の成長量は9,100万m3と同年に伐採した材積の3倍近くになっているんだそうです。
『こうしてこのプロジェクトは始まりました・・・』

こういった状況をなんとかしなければと、最近では国産材需要の回復を目指した様々な活動が行われています。私たちも建築に携わる人間として、この状況に手をこまねいているわけにはいかない!、ということで今回の国産材にこだわった家づくりというコンセプトは決定しました。
今まではパイン材等を使ったどちらかと言えば「洋風」な家が多かったので、今回のプロジェクトは『国産杉を使った真壁造の雰囲気のいい和風の家にしたい!』という漠然とした構想がありました。 ただ、ひとえに国産材のスギといっても、産地によってたくさんの種類があり、品質や価格もいろいろあります。
スタッフと色々検討した結果、今回は研修旅行で見学した高知県の土佐杉を使ってみることにしました。
野間の家 基本仕様
- ●構造材
- 柱・梁には全て土佐杉4寸材を使用した在来木造工法。2階床下地には、杉の間伐材を使った複合パネルを使い、床面での剛性を取りながら、1階の天井仕上げも兼ねさせることにしました。
- ●床・壁仕上
- 1、2階床材と2階勾配天井には全て無垢国産杉30ミリ厚を使用。 内装仕上にはこれも高知で見つけた土佐和紙の壁紙を使用することにしました。外壁仕上はセメントボードの上にコテ塗り材で仕上げます。
- ●断熱材
- 外壁、屋根とも硬質ウレタンフォームによる外断熱を採用。基礎断熱はシロアリを寄せ付けない発泡ガラス系の断熱材を基礎の外側に施工する基礎断熱を予定しています。
- ●設備
- 開口部には断熱ペアガラスサッシを使用して断熱性を高めます。火を使わずクリーンなihヒーターと電気温水器を採用したオール電化住宅。
- ●その他
- 玄関ドアは耐久性のある米杉材でできた無垢の特注ドアを使う予定です。外観のアクセントになっているポーチの木製引戸は、防犯の役目も持たせました。
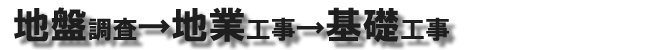
最近欠陥住宅の番組をよく目にします。そのなかでも『地盤沈下』による被害はかなり多いですね。どんなに頑丈な家を建てても、肝心の足元がおろそかでは全く意味がありません。私たちのウリは『とにかく頑丈な家づくり』何よりここに一番力を注いで工事をしています。
 |
 |
『表面波探査法』による地盤調査の様子です。 |
真ん中に見える銀色の物体は『起震器』と呼ばれます。 |
地盤調査の結果、『十分に耐力のある地盤改良の必要ない敷地』との調査結果が出ましたので、さっそく、地業(じぎょう)工事に取りかかります。
 |
 |
まずは重機で地面をならしていきます。 |
『栗石(ぐりいし)』と呼ばれるこぶし大の石を敷き、その上から細かい砂利を敷詰めて、ランマーで転圧していきます。 |
 |
その上から『防湿シート』を敷詰めます。このシートが地面から上がってくる湿気をブロックします。 |
防湿シートの上から『捨てコンクリート』を打設したあと、基礎の基準線を出す『墨だし』を行います。ここから型枠・配筋工事に入って行きます。
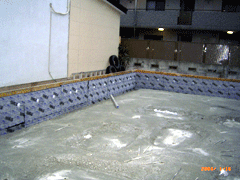 |
 |
基準の『墨』にあわせて外周部の『型枠』を立てていきます。 |
基礎の外側には、ガラスを発泡させたシロアリの被害を受けない断熱材を施工します。これで基礎は完全に断熱材に包まれます。 |
 |
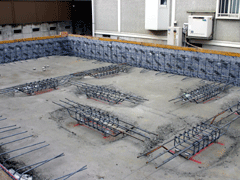 |
基礎の鉄筋を組んでいく『配筋工事』に入ります。まずは、外周部の立ち上がり部分から組んで行きます。 |
基礎の上にいくつか見える鉄筋の塊は、床下のメンテナンスをする際に、人が通れるように開けておく『人通口』の部分を補強する鉄筋です。 |
一見すると、鉄筋って何か頼りなく見えますが、基礎にとってはとても重要な部分です。なぜなら、コンクリートは圧縮力(押しつぶされる力)には強いのですが、引っ張られる力にはとても弱いのです。そのコンクリートの弱点を補っているのが鉄筋です。配筋工事の際には、鉄筋の本数・太さ・間隔等を現場で細かくチェックします。
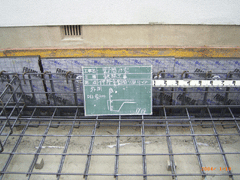 |
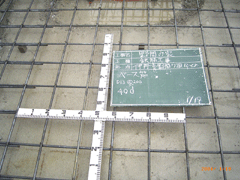 |
外周立ち上がり部分の鉄筋検査。右側に見えるスケールで鉄筋の間隔を測っています。 |
基礎ベース部分の鉄筋検査。太さ13ミリの鉄筋を200ミリの間隔で配置しました。 |
 |
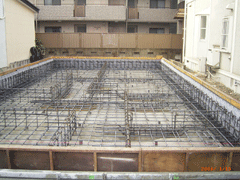 |
床下メンテナンス用の人通口部分の補強筋。基礎が途切れる部分なのでこの部分は念入りに検査する必要があります。 |
配筋を終えた基礎の全体写真。びっしりと鉄筋が配置されています。 |
 |
(財)住宅保証機構による配筋検査の様子です。検査してくれるのはいいんですが、必死で施工した型枠に足を乗せないでほしいなぁ… |
配筋工事が終わったら、いよいよコンクリートを打設していきます。まずは使用するコンクリートをチェックする『受入検査』を行います。ここで生コンの水分量・空気量・塩分量等を測定します。コンクリートは基礎の命なので、基準に適合しないコンクリートがあれば、ミキサー車ごと帰らせます。ここで手を抜いて、後で困るのはお客さんだけではなく我々も同じです。いつでも『自分の家を建てるような気持ち』で施工するよう心がけています。
 |
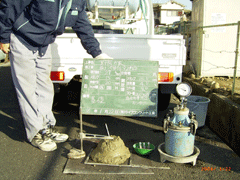 |
いよいよ生コン打設の日。現場にミキサー車が到着!生コンを送り込むポンプ車も待ち構えています。 |
『受入検査』の様子。真ん中に見えるのは検査用バケツに入れた生コンをひっくり返したもの。生コンの柔らかさを測る検査です。 |
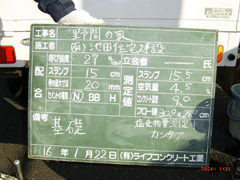 |
いろいろな検査をして、異常がないかを入念にチェック。検査にパスした生コンだけを使用します。 |
 |
 |
ついに打設が始まりました!ポンプ車につながれたチューブから勢いよく生コンが飛び出します。 |
型枠の隅々までコンクリートが行き渡るように、バイブレータを使って振動を与えていきます。これを怠ると、型枠を外したときに基礎の表面に穴が空いてしまい、構造上の弱点になったりします。 |
 |
生コン打設後、基礎の養生期間に入ります。冬場はコンクリートの反応が鈍るので、基礎の温度が下がり過ぎないように、シートをかぶせて養生します。 |
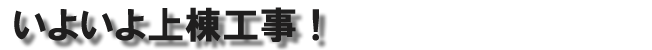
前回は家を支える土台となる『基礎工事』までをお伝えしました。今回からはいよいよ『木工事』と呼ばれる建物の工事に入って行きます!ここからは木工事の主役、大工さんが登場します。

左から池田・山崎(兄)・山崎(弟)・軒・山崎棟梁。
『野間の家』の中心メンバー勢ぞろいです。
腕がよくて人もよい『和み系大工』、と私たちは呼んでいます。
野間の家では構造材に無垢材を使い、『真壁(しんかべ)造り』という、柱・梁が室内側に露出する昔ながらの工法を使って造ります。
一般的な住宅とは違い、木を知り尽くした『大工』の技術がどうしても必要不可欠です。
山崎棟梁は失われつつあるその技術を持った大工さんの一人です。私たちも現場を見に行くたびにいろんなことを教えてもらっています。
さぁ、いよいよ木工事が始まります!
まず初めは、土佐杉の柱・梁を組み立てる『上棟工事』です!
 |
 |
まずは1階の土台・柱・梁から組んで行きます。柱は全て剥き出しの仕上げになるので、傷が付かないように紙が巻いてあります。 |
レッカー車で吊り上げられた梁をゆっくりと柱に差し込んで行きます。柱や梁は全て4寸(120mm)の部材です。 |
 |
柱の上部には『ほぞ』と呼ばれるでっぱりがあり、梁にはそれを差し込むための穴が空いています。それを手作業で丁寧に差し込んで行きます。 |
 |
 |
『追い掛け大栓継ぎ』という昔ながらの継手を使っています。これが組み合わさって梁をしっかり繋いでくれます。 |
追い掛け大栓継ぎを継いでいるところ |
2階床の下地には、杉の間伐材を利用して造られた『Jパネル』を使いました。このパネルで床水平面の剛性を取りながら、1階の天井仕上げも兼ねさせています。
 |
 ←↑1階天井を見上げたところ。梁と梁の間に見えるのが『Jパネル』です。これが梁とともにそのまま1階の天井仕上げになります。 |
 |
 |
斜めに掛かっている角材が、屋根の下地となる『垂木(たるき)』と呼ばれる部材です。垂木にも杉の4寸角を使用しています。 |
かなり組みあがってきました。ここまで来ると家の全体像がだいぶ分かりますね。 |
2階は柱や梁がすべて剥き出しになっています。天井仕上げとなる『野地板』には兵庫県産の杉材30ミリ厚を使いました。
 |
 |
野地板を屋根の上から見たところ。兵庫県の杉は赤みが強いのが特徴です。 |
吹抜け下から天井を見上げたところ。4寸角の垂木と野地板がいい雰囲気を出しています。 |
野間の家では、柱・梁のつなぎ目の部分に『込み栓(こみせん)』と呼ばれるピンを打ち込んで固定する工法を採用しています。手間は掛かりますがこれで十分な耐力を得られるんですから昔の大工さんってすごいです。釘やビスのない時代にはこういった方法で柱や梁を接合していたんですね。
 |
 |
『込み栓』を打ち込む山崎棟梁。こういう家をやっているときは本当に楽しそうです。 |
追い掛け大栓継ぎに打ち込まれた込み栓。こういった継ぎ目も込み栓で固定します。 |
梁や柱等の構造材が組みあがったところで、雨で構造体を濡らさないよう急いで屋根の工事に取りかかります。
まずは屋根の断熱材の施工に入ります。
 |
 |
野地板の上から『硬質発泡ウレタン』の断熱材を敷いていきます。継ぎ目には『気密テープ』を貼っていきます。 |
その上から、通気用の垂木をもう一度敷いていきます。この隙間を空気が流れるというわけです。 |
 |
通気垂木の上に屋根下地を敷詰め、屋根の仕上げをしていきます。 |
屋根工事はともかく、外壁を完全に包んでしまうまでは『雨』が最大の敵です。特に無垢材の場合は雨に濡れてしまうとシミになったりします。外壁工事が終わるまでは、毎日天気予報をチェックして、雨が降りそうな時は濡れないように外部をブルーシートで包みます。
 |
 ←↑雨のたびにブルーシートを貼るのは結構大変な作業です。大工さんの邪魔をしないように手伝ってみました。結構疲れました・・・ |
まだまだ工事途中ですが、『野間の家』の内部をご紹介。完成後の雰囲気を想像しながらご覧になってみて下さい!(画像をクリックすると拡大します)
 |
 |
1階キッチン部の天井を見上げたところ。土佐杉の梁とJパネルが絶妙にマッチしています。ここに照明がついてくるともっと雰囲気がでるでしょうね。楽しみです! |
1階吹抜けの見上げ。1階のJパネルのおとなしい感じとは違って、2階の兵庫県産の杉の荒々しい木目がいかにも『木』っていう感じですね。 |
 |
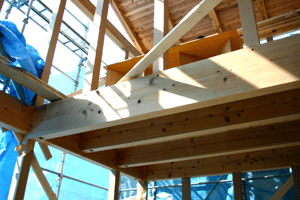 |
2階南側からみたところ。4寸勾配の優しい勾配天井が繋がっています。部屋の取り合いにはガラスをはめ込む予定です。 |
吹抜部に掛かる梁。『野間の家』に使われた中で一番大きな梁で、梁せい(高さ)は42センチもあります。どっしりと2階を支えてくれている頼もしい梁です。 |
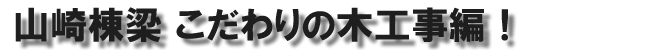
さて、前回は土佐杉の構造材を組み上げる「上棟工事」までをお伝えしました。
今回はいよいよ内部の床や壁などの造作を行う「木工事」に入っていきます。
 |
工事足場と養生ネットですっぽりと覆われた「野間の家」 ほんとに工事中?、というほど静かなこの現場の内部では、こだわりの棟梁、山崎さんの緻密な作業が繰り広げられていました。 |
 |
 |
雨で構造体を濡らしてしまわないよう、建物の外周は全てブルーシートで包まれています。なので、昼間にも関わらず暗い!一瞬時間が止まっているような錯覚に陥ります。 |
その薄暗い空間の中で、大工さんの作業は少しづつ進んでいました。息子のヤスさんが他の現場に手伝いに行っているため、山崎棟梁一人で作業は進められています。右に写っているのは監督の軒です。 |
上棟後に一番重要なのは、いかに建物を雨で濡らさないか、ということです。
そのため、大工さんは筋かいや間柱などの取付を終わらせたあと、取り合えず窓の取り付けに入ります。
ただこの「野間の家」は昔ながらの「真壁造り」。現在最も普及している柱を全て隠してしまう「大壁造り」とは異なり、窓の取付にも通常以上に手間が掛かります。
 |
 |
さあ、現場にアルミサッシが搬入されてきました。野間の家では外部サッシには全て、結露を起こさない「断熱ペアガラスサッシ」を使用しています。 |
まずは、サッシが取り付く部分の梁などに空いている穴(梁と梁を緊結する為のボルトを止めるための穴)をふさぐ「埋木(うめき)」という作業から始めます。構造材が仕上げ材になる真壁の家ならではの作業ですね。 |
 |
 |
穴と同じ大きさの木材を埋め込み、表面が平らになるように磨いていきます。 |
埋木したボルト穴。少し木目が違う部分が分かるでしょうか?「本当は木目まで合わしたいんやけど、そこまでやると工期が延びて、池田さんが困るから(笑)」とは山崎さんの言葉。いやいやこれで十分ですよ。 |
真壁の家の場合、窓の上下に「鴨居」「敷居」を取り付けて、その間にサッシを取り付けます。この鴨居・敷居の取り付けが非常に難しく、まさに大工さんの腕の見せ所と言えます。
 |
 |
真壁のサッシの取り付けは上の写真のように、「鴨居・敷居」と左右の柱にはさまれるような形になります。この木と木の接合部は普通に施工すると、どうしてもすき間が空いてきてしまうんです。 |
そこで、手間は掛かりますが、鴨居(敷居)が取り付く柱全てに、先に「しゃくり」と呼ばれる溝をノミで浅く彫っておきます。 |
 |
 |
そのしゃくりに外壁側から鴨居(敷居)を差し込んでいきます。こうすることで、柱が若干動いても、柱との隙間が出来ないんです。 |
山崎棟梁が仕上げた柱と敷居の接合部。 |
サッシを付け終ったら、外壁の断熱材を張るために、バルコニーや庇などの外周りの作業を行います。
 |
 |
山崎棟梁、バルコニーの床を施工中。こういう作業でも棟梁は全く手を抜きません。 |
棟梁が仕上げた床の上に、今度は防水屋さんが防水処理をしていきます。 |
 |
続いて玄関の庇を造っていきます。 |
外部では外断熱の断熱材を張る工事が進む中、内部ではいよいよ無垢杉の床材を張る作業に入っていきます。どんな雰囲気になるか楽しみです!
 |
 |
まずは、2階床下地のJパネルの上に45ミリ角の根太を打っていきます。この隙間で電気配線を通すわけです。 |
その上から30ミリ厚の無垢杉材を一枚一枚張って行きます。野間の家の床は無垢の国産杉材を使用しています。 |
 |
 |
無垢の床材と柱の接合部分も隙間が出来ないように柱部分にしゃくりを入れています。 |
床材を張り終わったら、この後の工事で床材に傷が付かないように養生シートを張っていきます。杉材は特に傷が付きやすいので念入りに養生します。 |
外部では、玄関ドアの取り付け工事が始まりました。野間の家の玄関ドアは特注で造らせた無垢材の玄関ドアです。実は私は今回、このドアがどんな雰囲気になるのかが一番楽しみだったりします。
 |
 |
玄関ドアつり込み開始。このドアは「米杉(ウエスタンレッドシダー)」という木で出来た無垢のドアです。 |
無垢のドアはアルミと違い、重量が重いので、二人がかりでなんとか取り付けることが出来ました。なかなかいい感じです。 |
 |
 |
玄関ポーチ上には国産の無垢杉材を張っています。玄関ドア上部には採光のための防犯ガラス入りランマを取ってあります。 |
最後に塗装をして完成。やっぱり無垢材のドアって重厚感があってどっしりしてます。玄関錠には当然ピッキング防止錠を使っています。 |
さぁ、いよいよ内部では山崎さんが最後の仕上げとなる玄関框やカウンターなどの無垢の造作材の工事に入ります。長かった工事もいよいよラストスパートです!
 |
 |
玄関の踏み台となる「式台(しきだい)」のそりを修正する山崎さん。こういう大きな無垢材はどうしてもそりが出てしまいます。これをいかに直すかも大工さんの技量です。 |
玄関の上がり框。全て無垢の杉材でできています。カンナを掛けられた無垢材の表面はほんとに綺麗です。 |
 |
 |
子供室の勉強カウンターも造っていきます。本を置けるように少し上がったところに棚も造りました。 |
子供室収納内部。野間の家の収納の中は全て杉材を張り詰めています。無垢材の吸放湿効果が期待できそうです。 |
外壁仕上工事も終わり、いよいよ足場が外れ、野間の家の外観が姿を表しました。
内部では、山崎さん親子が壁の下地となる石膏ボードを張っていきます。
その上から土佐和紙の壁紙が張られていきます。さぁ、いよいよ待ちに待った完成です!
 |
 |
外壁工事が終わり、やっと野間の家の外観を見ることが出来るようになりました。イメージどおりの仕上がりに満足です! |
内部ではヤスさんが石膏ボードを張っています。真壁造りの家では、木材との取り合いが多いので、石膏ボードを張るのも手間が掛かります。 |
 |
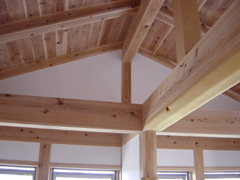 |
石膏ボードを張ると、部屋の雰囲気がだいぶ分かるようになってきます。手前に見えるのは山崎さんに造ってもらった杉材の階段です。この家の見どころの一つです。見学会でぜひ登って見て下さい! |
石膏ボードの上に土佐和紙の壁紙が張られました。素朴な風合いがなんともいい感じです。 |

長かった「野間の家」の工事も何とか終わり、いよいよ完成の日を迎えました。
大工の山崎さん親子を初め、この家を造るに当たって協力してくれた関連業者さん・職人さんの皆さんに改めて感謝したいと思います。
国産材の土佐杉材にこだわった真壁の家の完成写真はこちらでご覧になれます。
『杉にこだわった現代風の田舎家』
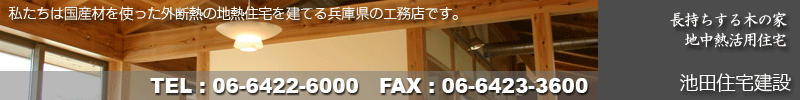
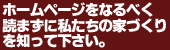
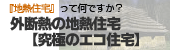
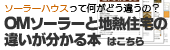
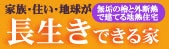
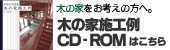
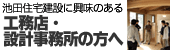
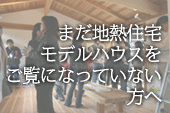
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)