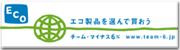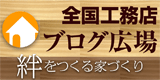その3 基礎工事
1.栗石地業


写真左:栗石地業
写真右:ランマーで突きかためをしているところ
「栗石地業」と呼ばれる作業の様子です。こぶしの大きさくらいの石を手作業で敷き詰めて、その上から目つぶしと呼ばれる、さらに細かい石を敷いて、「ランマー」で平らに突き固めます。
2.防湿シート敷設


写真左:防湿シート施工中
写真右:全体に敷きつめます。
「防湿シート」(ポリエチレンフィルム)を敷き詰めているところです。「防湿」という名前の通り、地面からの湿気が床下に上がってくるのを防ぎます。ビニールハウスにも使われている材料なので丈夫です。
あまり意味がないように思われるかもしれませんが、シートを敷き終わってしばらくすると、シートの中は水滴だらけになります。それだけ地面から上がってくる湿気は多いのです。
3.捨てコン打設・墨出し


写真左・右:防湿シートの上に捨てコンを打設していきます。
防湿シートの上から「捨てコンクリート」(捨てコン)を、厚さ5センチほど打設します。
これは「捨て」という名前でわかるように、強度を期待するものではなく、地盤面を平らにして基礎の位置・幅などを正確に計りやすくするための下地のようなものです。

写真:捨てコンの上に墨出しをしているところ
この上に「墨出し」(基礎の位置を正確に出す作業)を行います。その「墨」を基準に、その後の作業は進められます。
4.配筋工事・型枠工事・基礎断熱工事

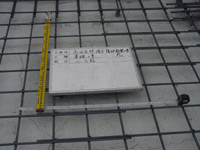
写真左:配筋の様子
写真右:ベース筋間隔の検査
捨てコンの墨を基準にして「型枠」を立てて行きます。
外周部に関しては、基礎部分を断熱するために発泡ガラスでできた住宅基礎用断熱材「コリグラス」を型枠がわりに使います。
こうすることで、建物はすっぽりと断熱材に覆われることになり、断熱性能が飛躍的に向上します。
その後、基礎の骨格となる鉄筋を組み立てる「配筋作業」に入ります。
まず、外周部の立ち上がり部分から組み始め、徐々にベタ基礎ベース部分まで進めていきます。この作業にだいたい3日くらいかかります。
基礎は、コンクリートと鉄筋が組み合わされて、初めて強度を発揮します。
なぜなら、コンクリートは圧縮(押し潰そうとする力)にはとても弱いのです。それに対して鉄は引張に強い性質を持っています。
ですから、どちらもおろそかにしてはいけないのです。
配筋作業には…
・「鉄筋同士のつなぎ目の定着長さ」がとれているか
・「鉄筋同士の間隔」がとれているか
・「開口部分の補強筋」は正しく配置されているか
・「コンクリートのかぶり厚さ」はとれているか
などのチェック項目があります。
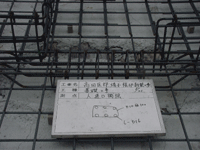
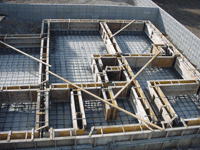
写真左:人通口の開口補強筋
写真中:配筋が終わると、中枠を立てていきます
写真右:(財)住宅保証機構の検査員による「配筋検査」の様子
5.コンクリート受入検査・生コン打設


写真左:生コン受入検査。生コンの水分量、塩分濃度、空気量などを測定
写真右:いよいよ生コン打設開始。ミキサー車からポンプ車にコンクリートが流し込まれます
いよいよ、型枠に生コンを流し込む打設作業に入ります。
まずは現場に納入されたコンクリートに異常がないか検査します。
真ん中に見えるのは、「生コン」を検査用のバケツに入れてひっくりかえしたものです。
ひっくりかえして、生コンが何センチ崩れたか、その値を調べます。この値を「スランプ値」といい、生コンの水分量を知る大事な数値になります。
コンクリートの品質は鉄筋の錆びや、基礎のクラックなどを防ぎ、基礎の寿命を長くするためにも重要なところですから、しっかり検査する必要があります。


写真左:ポンプから生コンが飛び出します
写真右:すぐにならしていきます
6.型枠解体・養生期間

写真:基礎養生中。硬化するにつれて表面は真っ白になっていきます。建物のおおまかな形がわかるようになってきました
生コン打設後、1・2日置いてから型枠を取り外します。十分に固まっているように見えますが、まだコンクリートは本来の強度まで硬化していません。
ここから上棟までの間、基礎の強度がでるまで「養生期間」を置きます。夏場であれば、約7日間、冬場は2週間くらいです。
養生期間が終わるといよいよ上棟工事に入ります。
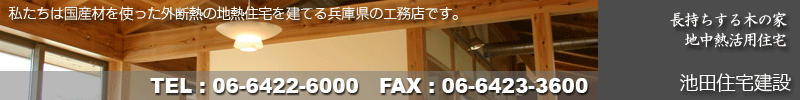
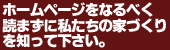
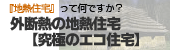
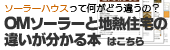
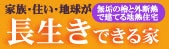
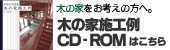
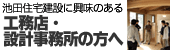
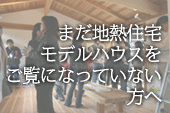
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)