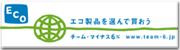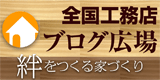その4 上棟工事・木工事
1.土台引き

写真:土台引きをしているところ。この土台が家全体を支えています
いよいよ、家の骨組みを造る上棟工事に入ります。
ここからは大工さんの出番です。
まずは基礎の上に、建物を支える「土台」とよばれる材料を敷いていく「土台引き」という作業に入ります。
土台に穴を開け、基礎から飛び出してくる「アンカーボルト」を通し、上からナットで締め付け、基礎と構造体をしっかり緊結します。
2.梁・柱への金物付け

写真:金物付けの様子。図面を確認しながら金物をつけていきます
土台引きと共に、やっておかなければならないのが、梁や柱へ接合金物を先付けしておく「金物付け」です。
特に金物工法の場合は、接合金物が構造のメインとなるので、間違いのないように図面を確認しながら、一つずつボルトで留めていきます。
ここまで終われば、さあ、明日はいよいよ上棟です!
3.上棟工事


写真左:レッカー車で部材を吊っています
写真右:梁と柱を繋いでいるところです

いよいよ「上棟(棟上げ)工事の日」です。
家づくりの中で、もっとも慌ただしい一日のはじまりです。レッカー車で部材を吊って、大工さんがそれを組んでいきます。
この日は、大工さんや監督さん、業者の人たちで現場はごったがえします。
1日で屋根の下地まで完成しないと、家の骨組みが雨などで濡れていまう可能性があるので、大工さんは応援を呼んで、5・6人で仕事をします。
※金物工法って?


写真左:在来工法の仕口とほぞ
写真右:梁、柱を繋ぐ接合金物

写真:柱の横からピンを打ち込んで固定
今までの在来木造工法では、柱と梁、あるいは梁と梁の接合は大工さんが、1本1本ノミやカンナで削ってつくる「ほぞ」や「仕口」と呼ばれる凹凸によって、接合されていました。
しかし、施工性の問題や、構造体を直接切り欠くため、どうしても「断面欠損」が大きくなり、構造上の弱点になっていました。
金物工法とは、それらの接合部に特殊な金物を使うことで、なるべく構造体への切り欠きをなくし、また「ドリフトピン」と呼ばれるピンを使って接合する事で、施工性とともに強度の上げる事ができる次世代の木造工法です。
4.2階床剛床仕様


写真左:構造用合板を張っているところ
写真右:2階床全景
2階床には従来の「根太」を使わず、梁を約90センチごとに配置して、その上に構造用合板28ミリを張る「剛床」仕様を採用しています。
こうすることによって、構造体と床面が一体化し、地震や台風などの横からの力に対して、「面」で支える形になり、強度がアップします。
5.小屋組作業

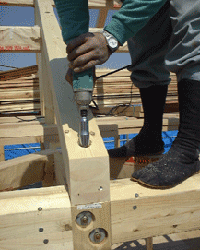
写真左:ラグスクリュー
写真中:ラグスクリューを留めているところ

写真:一番高いところにある梁が棟木。斜めにかかっているのが垂木です
屋根の下地となる「小屋組」を組んでいます。
一番高いところにある梁「棟木」から「桁」にかけて、「垂木」とよばれる材料をななめに架けていきます。
垂木は10.5センチ角の材料を90センチ間隔で配置し、梁に対して「ラグスクリュー」という特殊なビスで留めていきます。
6.野地板張り


写真左:野地板を張っているところ
写真右:室内側から見たところ。これがそのまま天井仕上げになるため、工程を一つ減らすことができます
垂木をかけおわったら、その上に「野地板」を1枚1枚ビスで張っていきます。
野地板には赤松の30ミリ厚の無垢材を使い、これが屋根の下地と共に天井仕上げも兼ねています。
7.屋根外断熱材敷設・通気用垂木施工

写真左:気密テープ施工


写真左:断熱材を張っていきます
写真右:通気垂木を留めているところ
野地板を張り終わった後、外断熱用の断熱材「硬質ウレタンフォーム」を隙間なく張っていきます。
継ぎ目には「気密テープ」を張り、外気の流入を防ぎます。
断熱材を張り終わると、その上に通気層を確保するための45ミリ角の垂木を30センチ間隔で留めていきます。
この垂木の間の通気層を空気が流れて、熱と湿気を排出する仕組みになっています。
8.屋根工事
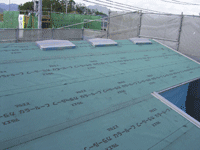

写真左:アスファルトルーフィングを張り終わったところ
写真右:カラーベスト施工中
通気層用の垂木の上に、屋根仕上げ用の構造用合板12ミリを全面に張った後、屋根の工事に入ります。
まず防水用の「アスファルトルーフィング」を全面に敷き詰め、その上から「カラーベスト」を張っていきます。
これで屋根の工事は終了です。
構造体を雨などで濡らさないようにするためには、ここまでの工事をいかに早くできるかが、重要なポイントです。
9.筋交い・間柱施工

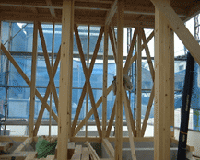
写真左:筋交い施工中
写真右:×になっているのが筋交いです
屋根工事が終わると、大工さんが内部の工事に入ります。
まずは「筋交い」・「間柱」の取り付けから始めます。
特に筋交いは、建物にかかる横方向の力を支える大事な部材ですから、構造計算で出された位置に図面を確認しながら1本ずつ施工していきます。
また間柱は、外部の断熱材や外壁材を支えるために45×105ミリとかなり大きめの部材をつかいました。
10.木酢液散布
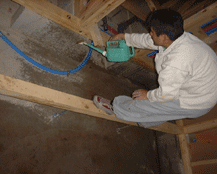

写真左:木酢液を散布しているところ
写真右:強烈な炭の匂いがします
床下に防虫のための「木酢液」を散布します。
木酢液とは、木炭を作るときに同時に得られる樹木のエキスのようなもので、木酢液の中には、200種類もの成分が含まれています。植物の生育を促進したり、病害虫の防除やカビなどを生えにくくする性質、消臭の効果などがあります。
外断熱、気密住宅なので、基本的に床下は室内と同じ環境になるため、危険な薬品は使わずに自然の素材を使用します。
11.外部サッシ取付工事


写真左:サッシを取り付ける下地を検討中
写真右:サッシを取り付けたところ
外部のアルミサッシを取り付けていきます。
開口部はどうしても熱が逃げやすく、入りやすい部分です。
熱の流入、流出を少しでも抑えるため「断熱ペアガラスサッシ」を使用しています。
このサッシを使うことで、熱の移動が少なくなり、冷暖房の効率がよくなるだけでなく、冬場の結露を完全に抑えることができます。
12.外壁外断熱工事・通気胴縁工事

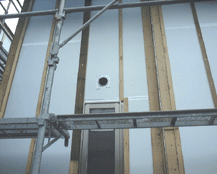
写真左:断熱材を張り終わったところ。継ぎ目には気密テープを張っています
写真右:上下に走っている木材が胴縁。この間を空気が移動します
外壁にも同じように断熱材を外側から張っていきます。
サッシとの取り合い、断熱材同士の継ぎ目には気密テープを張っていきます。
断熱材を張り終わると、その上から通気層を確保するための「胴縁」という木材を外断熱専用の長いビスで留めていきます。
こうすることによって、胴縁の間を空気が移動し、熱を上方に逃がしてくれます。
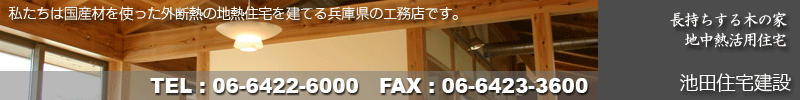
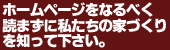
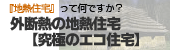
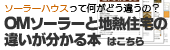
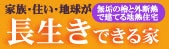
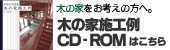
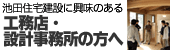
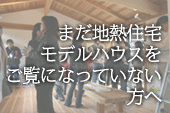
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)