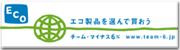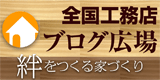※在来木造工法って?


写真左:柱の上に飛び出している部分がほぞ。梁の下にこれと同じ穴があけてあり、そのにこのほぞを差し込みます
写真右:梁の上に当て木をして「かけや」と呼ばれる大きな木槌で叩きながらしっかりと組んでいきます
この住宅では、柱・梁などの構造材に高知県産の「土佐杉」を使用しています。
在来木造工法では、部材同士の接合部(継手・仕口)は「ほぞ」と呼ばれる凹凸のを組み合わせつことによって成り立っています。
この接合部は、どうしても木材の「断面欠損」が大きくなってしまい、構造上の弱点となってしまいます。
この住宅では、断面欠損が特に大きい「通し柱」には、一般的に使われる3.5寸(105ミリ)よりふたまわり大きい「5寸角(150ミリ)」の角材を使用。その他の柱材は「4寸角(120ミリ)」の材料を使い、構造の強化を図っています。
追い掛け大栓継ぎ

写真:追い掛け大栓継ぎ
梁と梁の接合部には「追い掛け大栓継ぎ」とよばれる継手を使用しています。
部材同士の接地面積が大きい、非常に優れた継手ですが、加工が難しいため現在ではなかなか使われることはありません。
この住宅では、この難しい継手をプレカット工場での「手作業」の加工を取り入れることにより、現場での省力化とコストダウンを図っています。


写真左:追い掛け大栓継ぎを継いでいるところ
写真右:梁の両端にこのような加工がされており、この2枚を合わせることで梁と梁を接合します
こみ栓工法


写真左:ほぞにあけられた穴に、梁を貫通させて、こみ栓を打ち込みます
写真右:こみ栓を打ち込んでいるところ
この住宅では、柱と梁の接合部にほぞを使っていると説明しましたが、ほぞだけでは引き抜く力がかかったときに簡単に抜けてしまいます。
そので、この住宅では、ほぞの引き抜き防止のために「こみ栓」とよばれる小さな木の棒を打ち込んで固定しています。このこみ栓が「ピン」のような役割を果たし、柱と梁をしっかりと緊結します。
こみ栓工法は、昔の日本建築ではよく使われていましたが、最近では手間が掛かることからほとんど使われなくなっています。
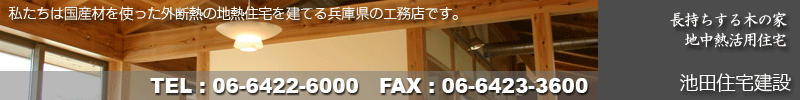
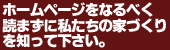
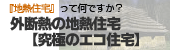
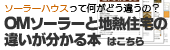
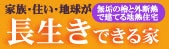
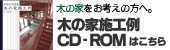
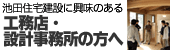
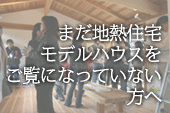
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)