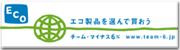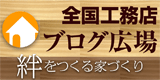田舎・都会に関係なく、関わりの度合いを決めるのは自分自身なんだろうな
田舎暮らしの両親が、ご近所の皆さんに助けられて、無事父の入院生活を乗り切った話を書きましたが、現在、施設でお世話になっている義母も、認知症が出始めた頃よく「最近はご近所同士で、通りへ出て話さへんようになった」と寂しそうに言っていました。
母は、大阪市内で一人暮らしをしていましたが、父が亡くなった後の寂しく手持ち無沙汰な時期を埋めてくれていたのが、ご近所の皆さんとの他愛ない話だったんじゃないかと思います。
もちろん、離れて暮らす子供達や友人、親戚もその役を担っていたとは思いますが、玄関を1歩出るだけで、色んな話の出来るご近所さんは得難いものだったようです。
母は今年92才で平均寿命と比べても長寿と言えます。そんな母がよく「長生きも寂しい」と言っていました。それは同世代のご近所さんや学校時代からの友人など“同じ時代を共有した”“同じ思い出を語り合える”人を順に失う事にあった気がします。これは、子供達がいくら、がんばっても埋められないものだと思います。
前回、私はご近所との関わりを田舎独特の物のように書きましたが、よく考えると母の住んでいた大阪市内にもご近所との関わりはあったようですし、同じく大阪市内に住む義姉などは、商家に嫁いだせいもあるかと思いますが、町内会や婦人会など結構ディープな関わりを持っているようです。
さて少し話は変りますが、三田のニュータウンに引っ越して娘を小学校に入れたときに、元々三田にお住まいの校長先生、教頭先生がよく「子供は地域で育てるもの」と仰っていました。
「ご近所のおっちゃん、おばちゃん皆が見てると思ったら、子供は悪さなんか出来ない」という事でしたが、当時私も含めお母さん達は「そんな古臭いこと・・・」と口々に言い合いました。
でも、最近の子供が犠牲になる事件の多発を見ていると、今更ですが、あの時の先生の言葉が甦ります。古い町や田舎のように、何代にも渡ってそこに住んできた人のいないニュータウンでは、当初どうしてもそういう意識は薄かったと思います。
只、ニュータウンも少しずつ歴史が出来てきたことに反映されてか、“町ぐるみで”という風潮が出てきているように思います。
毎朝、小学校の登校時にパトロールに立ってくださる方の顔は、私が越してきた当時40台の働き盛りだった方が多く、「〜さんも定年を迎えはってんなぁ」と思ったりします。
最近になって私も、地域との関わりは子供だけでなくリタイア世代にも重要な事なんだろうなと思うようになりました。又それは、田舎・都会に関係なく、関わりの度合いを決めるのは自分自身なんだろうなと思ったりしています。
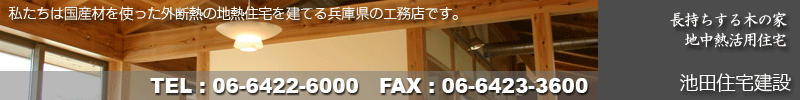
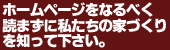
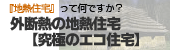
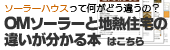
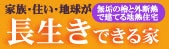
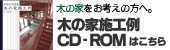
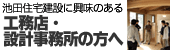
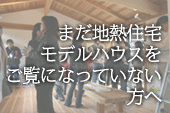
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)