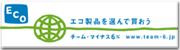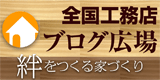高野山へ行って来ました。
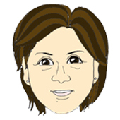 横山
横山
もう何年も前から「行きたい」「行きたい」と思いながらも
「近いのでいつでも行ける」と先延ばしていた“高野山”。
国内の各地から、果ては海外の方まで、
皆さん遠方の方が絶賛されているのを見聞きし、
関西人としては「行きたい」から「いかねばならぬ」(笑)となっていました。
ですが、いざ行こうと思うと、近いんですが、遠いんです!
三田から公共交通機関を使うと上手く乗り換えられて約3時間、乗り換えに失敗すると・・・という事で、9月の最終の水曜日、朝7時に車で出かけました。
高野山は海抜約900mに在るので山道を登ります。
舗装されてカーブが少ない国道480号がお勧めと調べていたので、阪和道を岸和田和泉インターで下り、480号と思っていたら、ナビが違うルートへ誘導します。
我が家のナビは2年前に情報を書き換えているので、そう古くは無いと思うのですが、
和歌山の道路が、一般道も高速も急速に良くなっているようです。
事前調べでも、ナビだけでなく最新情報を調べて出掛けた方が良いと有りましたが、
正にそうでした。ナビと意見が合わず、少し迷いましたが、10時少し前に無事到着です。
金剛峰寺前駐車場に空きを1台見つけ、
1593年に再建された金剛峰寺正門へ。
昔 この門は天皇・皇族、
高野山の住職しか
出入り出来なかった門だそうですが、
今は老若男女、
海外も欧米系の方が大勢通ります。
高野山の建物の屋根の多くは、当時寒過ぎて瓦葺に出来ず、桧の皮で葺いた桧皮葺です。
雨水を溜めておく天水桶等、火事との戦いが伺えます。
これ、前夜、録り溜めていたブラタモリ高野山編で予習したのを実感しました。
沢山の襖絵や、国内でも最大級の石庭、蟠龍庭(ばんりゅうてい)や
2000人分のご飯が炊ける2石釜等、何かとスケールの大きさを感じました。
続いて弘法大師が高野山で最初に 造営したという壇上伽藍へ、
僧侶が集い修行する閑静清浄な所でいくつものお堂が建ち並びますが、
その中心部に、
弘法大師が修行をしていた唐から、
伽藍を造る場所を占うために投げた三鈷
(密教の法具)が引っ掛っていて
この地に決めたという“三鈷の松”があります。
この松、中に松葉が3本の物が有り、
見つけるとご利益が有るという事で、
若いカップルが探していました。
と、私も発見!お財布に入れときます。
この後、諸大名等、有名な人々の供養塔が有り、弘法大師が今も眠っておられるという、奥の院へ。御廊橋より奥はカメラの撮影は禁止になっていてどうなっているんでしょうか?
びっくりしたのは、普通に、一般の信者さんが、納骨をされる場所なんです。
お墓なので当たり前なんですが、大抵の方が、見物・観光でお参り?するイメージが私の中で一人歩きしていたので、ご家族の遺骨を納骨され、熱心にお参りをされる光景を見て、何だか目が覚めたような感覚でした。
高野山を後にして、紀伊山地の霊場と参詣道として、同じく世界遺産に指定された丹生比売神社にお参りし、帰途に着きました。
この世界遺産には、もちろん熊野三山、そして吉野・大峯が入っているんですが、これまた近くて遠いので、なかなか行けない場所ですが、近いうちにぜひ出掛けたいと思っています。
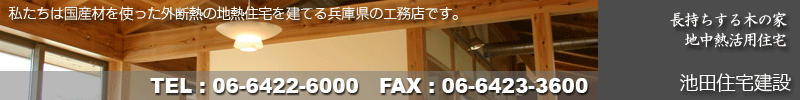



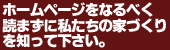
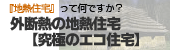
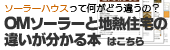
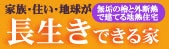
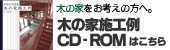
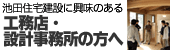
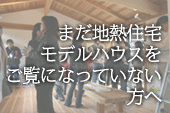
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)