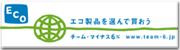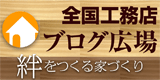京都市北区へ・・・
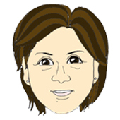 横山
横山 外国人観光客受け入れが再開されました。
急がねば!!と京都へ、今回は京都市北区を中心に・・・。
午前中仕事の夫が帰宅するやいなや、
おにぎり弁当を食べながら、上賀茂神社へドライブしました。
.
上賀茂神社は、京都の一の宮で
天武天皇の御代(678年)に現在の
御殿の基が整えられたという
とても古い神社で、特別参拝をしました。
国宝の本殿、権殿近くでお参りが出来、神職さんの説明も聞けますが、
500円というお値段です。行かれる機会が有れば、ぜひお薦めです。
次の大徳寺はお茶の世界とご縁が深く、塔頭の聚光院は三千家の菩提寺ですし、
千利休切腹の原因になったとも言われる利休の木像のある三門は有名ですが、
塔頭も含め非公開が多いのが残念です。
拝観可能な大仙院では、平日の雨の夕方で、とても空いており案内をして頂きました。
応仁の乱で京都が焼け野原になり、一斉に再興されたので、材料不足で柱が細く、
茅葺き屋根を瓦にしたくても出来ないというお話が印象的でした。
いよいよ雨がひどくる中。
今宮神社でお参りをし、参道の一文字屋和助であぶり餅を頂きました。
この店は西暦1000年創業の老舗で、
その当時の井戸を今も使っているという、何とも京都らしいお店です。
きな粉風味の小さな餅のあぶったのに白みそダレの掛かったあっさり、
素朴で美味しかったです。
この日は、御所の近くに宿をとりました。
二日目は、御所近くの御王神社へ。
ここはイノシシとご縁が深く、
狛犬ではなく、駒イノシシが鎮座しています。
全国の猪年生まれの会が有るそうで、
猪年生まれの夫が、用紙に記入すると、
記念品を頂きました。
近くのとらやで、遅めの父の日に羊羹を買い、
清少納言が“丘は船岡”と讃えた船岡山に在る、
建勲神社(たけいさおが正式ですが、
電話をすると、けんくん神社です
と仰いました。)へ、
織田信長を祀っていて、ここからの眺めはなかなかで、
晴れていればもっと良かったろうと思います。
次は、世界遺産の龍安寺へ。
外構人観光客はほぼ居ませんが、
修学旅行生は、復活しています。
最近はバスで一斉に動くと言うより
グループ行動のようで
路線バスで動いている子達も居れば、
観光タクシーで移動するグループも有り、
隔世の感が有ります。
お隣の仁和寺は天皇家から住職を迎える門跡寺院という事で、
御殿は建物、庭共に豪華で見る物は多いのですが、やはり修学旅行生が多く、
混んでいたのと、前日の雨が上がり、蒸し暑いので、集中力が途切れます。
近くでおそばを頂き、千本釈迦堂、大報恩寺へ。応仁の乱で焼けなっかた本堂は創建時
(1227年)のままで、京洛最古の建物で国宝です。本堂も霊宝殿の数々の仏像も見応え
が有り、とても空いている穴場です。
最後は北野天満宮へ、
平日だからか大きな駐車場は無料で、
『まりなげ禁止』の看板を
見つけうれしくなりました。
天満宮でお参りを済ませ、すぐ近くの平野神社へ足を延ばし
“老松”という和菓子屋さんで、“夏柑糖”という、夏ミカンの器に果汁を寒天で固めた
季節限定のお菓子を買い、天神堂でやきもちを買って、食べながら帰途につきました。
2日間で、ご朱印12個、
とても暑くて汗びっしょりでしたが、時折吹く風がさわやかな旅でした。
夏は苦手で動かないと決めていましたが、結構アリかな、と思ったりです。
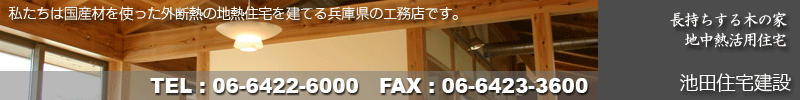





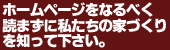
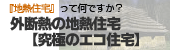
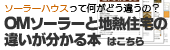
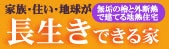
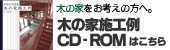
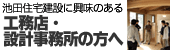
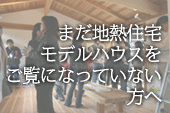
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)