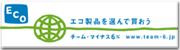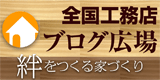1年ぶりの京都
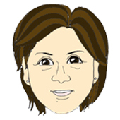 横山
横山早いもので二十四節気の“立秋”七十二候も二候目
“寒蝉鳴(ひぐらしなく)”の頃でしょうか?
ヒグラシが「カナカナカナ」と甲高く鳴く頃を表した候です。
セミは、4月下旬頃「ゲーキョ ゲーキョ」と鳴くハルゼミ、
6月頃から「チィー」のニイニイゼミ、そして7月中旬、
梅雨明けから一斉に鳴き出すミンミンゼミ、アブラゼミは、
特にうるさいと言うか、暑苦しいですね。
ですが、ヒグラシの季語は秋で、実際「カナカナカナ」を聞くと晩夏の少し切ない感じがします。
が、実際は7月頃から鳴き「ミンミン」が終わる日暮れ頃聞く事が有り、季節間違ってない?
と思っていましたが、立秋を過ぎ日中も気温が下がって来ると日中でもよく鳴き、
“寒蝉鳴(ひぐらしなく)”となるようです。
梅雨入り直前、1年ぶりに京都へ行きました。昼頃到着し八坂神社近く
“いづ重のお稲荷さん”を昼ご飯に頂きます。
うん、これこれ、麻の実が良いアクセントです。
大谷祖廟まで坂道を上がり、健康にお参り出来、美味しいお稲荷さんまで
頂ける事に感謝します。
次に、あまりの人の多さにずっと二の足を踏んでいた“高台寺”へ。
秀吉の冥福を祈るため正室ねねが建立した寺で、秀吉、ねねの霊廟でもあります。
この近辺は“ねねの道”と名付けられ、店が立ち並び日本人外国人を問わず、
着物を着た観光客の多いエリアです。
そして、昨年父の日に送り好評だった、パリパリの皮に自分であんこを詰める最中を
買いに、北野天満宮の南、“中村製餡所”へ。
ホテルに荷物を預け、秀吉が、市内あちこちに在った寺を集めたという
寺町へ夕食がてら出掛けます。“行願寺(革堂)”は、創建した行円上人が鹿の皮を
まとっていた事から革堂(こうどう)と呼ばれているそうです。
“下御霊神社”は、平安時代に冤罪を被り亡くなった貴人の怨霊を御霊
(ごりょう)として祀り、疫病災厄から朝廷と都を守る神社という事です。
付近には、古書店や骨董店が点在しますが、ショーウインドウにガレの一輪挿し、
16万円なり! 敷居が高く、店内には入れません。
そこへ外国人と思しき家族連れ、ガンガン子供連れで入店です。
「割らんといてよ!」おばちゃんは心の中でつぶやいてしまいました。
次の日、まずは“安井金毘羅宮”。テレビでよく紹介される“縁切り、縁結び”の神社です。
写真の白いお化けみたいな物、大量の形代(身代わりのお札)で全く見えませんが、
巨石(碑)だそうです。

神社のHPによると、形代に切りたい縁・結びたい縁等の願い事を書き、
それを持って念じながら真ん中の穴を表から裏へをくぐり、まず悪縁を切り、
次に裏から表にくぐって良縁を結び、最後にその形代を碑に貼るんだそうです。
若い女性の行列が出来、順番にそのお参りをされてましたが、
縁切りなのか? 良縁なのか? どちらを願うんでしょうか?
次は京都最古の禅寺“建仁寺”へ。国宝風神雷神図屏風で有名ですが、
法堂の天井に描かれた、阿吽の口をした双竜図もとても見応えが有りました。

最後に“六波羅蜜寺”へ。創建は空也上人で、御本尊で国宝の十一面観音は、
秘仏で見れませんが、口から南無阿弥陀仏が飛び出してる有名な空也上人像が宝物殿で見れます。
京都は行きたい所が多く、ついつい忙しく駆け足になってしまいます。(苦笑)
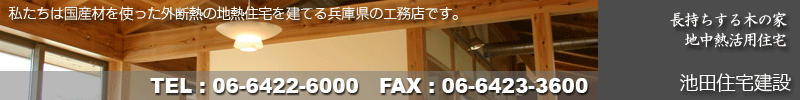
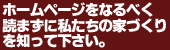
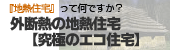
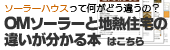
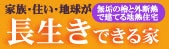
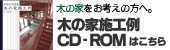
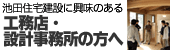
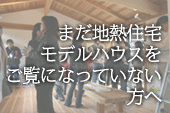
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)