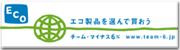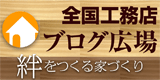勾配天井と配管スペースの両立
基本的に1階は天井仕上げをするので、天井ふところ(天井と2階床までの間のこと)さえあれば配管を通す事が出来るわけなんですが、電気配線のような細いものならともかく、換気ダクトは太さ100〜150ミリもあり、十分なふところを確保しておかなければいけません。
で、地熱住宅研修では『十分な配管スペースをとるために建物を高めに設定して下さい』とのことでした。
ここで、建物の高さについてちょっと触れたいと思います。少し専門的な内容も含みますが、さらっと読んで下さいね。
<軒高と階高>
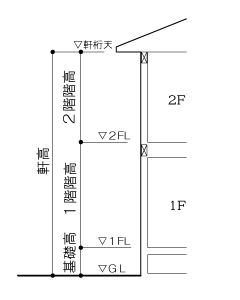
建物の建っている地盤面から、屋根を支える梁(軒桁)の上までの高さを『軒高』、ある階の床からその上の階の床までの高さを『階高』と言います。
ちなみに池田住宅の標準階高は
2,730mm+2,400mm=5,130mm
地熱住宅資料の参考階高は
3,100mm+2,900mm=6,000mm
その差なんと870mmです。つまり単純に地熱住宅にする場合は今より870mm家を高くしてください、ってことです。
『だからどしたん?家高くしたらええやん』と思われるかも知れませんが、家を高くすることで外壁・内部の仕上げ面積が増えたり、階段の段数が増えたり、外観のバランスも悪くなったりと、あまりいいことはないんです。
また広〜い敷地で建てる場合は別ですが、都市部の狭小地では『北側斜線』などの高さ制限に掛かる可能性も出てきます。
なので、建物の高さって結構重要です。今回の敷地では問題ないとしても、斜線制限の厳しい敷地で家を建てることの多い池田住宅としては、少しでも『高さの低い地熱住宅』が出来るようにしておく必要があります。
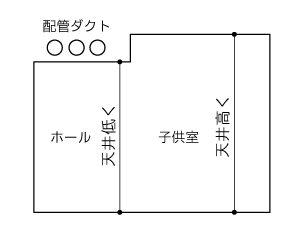
そこで、今回は階高を変えずに配管スペースを取るために、左の図のように配管を通す部分のみ1階天井高を下げる、という方法を取る事にしました。
つまり、天井高の必要な部屋は高く、逆に玄関ホール、トイレや洗面などの空間は低く設定し、ふところの多い部分を使って各部屋に換気ダクトを配管するんです。
また、2階に関しては今までと同じ、『全て勾配天井仕上げ』にしながら、各部屋に配管する方法を考えることにしました。
方法としては、家の中心の小屋裏に換気システムをまとめ、そこから放射状に各部屋に配管するという方法です。
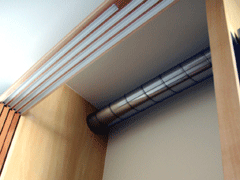
しかし当然天井のない部分なので、配管が室内に露出してくることになります。
これら見えてくる配管を極力少なくして、最悪露出してくる配管は露出専用の化粧配管(スパイラルダクト)を使ったりする事で隠す事にしました。
数本の配管を隠すためだけに全て天井を張ってしまうのではなくて、本当に必要な部分のみに細工をする。一番無駄のない合理的な方法だと思います。
人気ブログランキングに登録しています。こちらをクリックして応援宜しくお願いします。

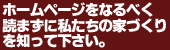
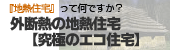
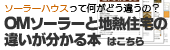
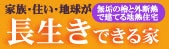
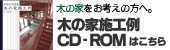
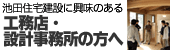
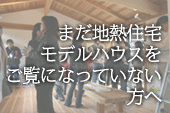
![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)